| 乳がん、子宮頸がん検診 「受診しない人に罰則を」「学校でも教えて」 「成人式で検診促す」・・・ 検診受診率アップで具体的な提案次々と NPO法人・医療福祉ネットワーク千葉 第3回 市民公開講座 「ストップ!女性のがん 早期発見がすべてです」 2011年1月16日 (クリックしてください) |
 |
| 乳がん、子宮頸がん検診 「受診しない人に罰則を」「学校でも教えて」 「成人式で検診促す」・・・ 検診受診率アップで具体的な提案次々と NPO法人・医療福祉ネットワーク千葉 第3回 市民公開講座 「ストップ!女性のがん 早期発見がすべてです」 2011年1月16日 (クリックしてください) |
 |
 |
|
|
| イギリスでは未受診者に“督促状” |
| 「日本の子供たちは病気を防ぐためにはどうしたらいいか教わらないまま大きくなる。がん検診を受けなければという意識もない」。市民公開講座のパネルディスカッションで、自治医科大附属さいたま医療センター産婦人科の今野良教授はこう警鐘をならしました。今野教授によると、イギリスでは中学や高校で学年に応じて子宮頸がんのワクチンについて教える機会が設けられているといいます。理科や社会の授業の中で触れることもあるほど。さらに、自治体が行っているがん検診では“検診への招待状”が全員に届き、一回目で受診しなければ二回目、三回目と今度は“督促状”が来て、最後は電話で呼び出されて受けざるを得ない状況に持っていくのだとか。「生活困窮者の人には生活保護の団体の保健師が促す」ほどだといいます。 乳がん体験者で皮膚科医、NPO法人・がん患者団体支援機構の浜中和子理事長代行は、全国の学校を訪れて子宮頸がんや予防ワクチンについて講演している産婦人科医の知り合いのことを紹介し、「学校のカリキュラムにがんのことを位置付けてきちんと教えてほしい」と指摘しました。さらに成人式で自己検診のパンフレットを配布するなど啓発活動をもっと工夫するべきだと提案しました。千葉県がんセンターの田中尚武婦人科部長も、子宮頸がんはワクチンで予防が可能であると実証できたことを説明して、「がんは予防できるという新しい時代に入ったという認識を広く持ってもらいたい」としました。NPO法人・医療福祉ネットワーク千葉の竜崇正理事長は「健康のことに関心を持ってもらい、検診で予防するということを学校教育で教えて込んでほしい」と語り、子供のころから自分の健康を自分で守る力をつけられる教育こそ、これからのがん医療に求められている大事な役割でもあると強調しました。 |
   |
学校でのがん教育には「壁」も |
| 一方、学校教育の中で女性の乳がん、子宮頸がんを取り上げるには学校現場ならではの問題もあるといいます。それは、「性教育」という言葉と、「予防ワクチンの集団接種」に対する抵抗感がぬぐえないこと。今野教授は「性教育ではなくあくまでも健康教育と言わなければならない。性教育というと途端に反対者が出て、公的教育の場から外される」と注意を促しました。集団接種も同様に厚生労働省からの指導で簡単には実現できないといいます。特に、子宮頸がんの予防ワクチンをより多くの子供たちに接種してもらうには、「この二つの荷物を抱えていっぺんに山に登るのではなく、別の形で解決して行く」(今野教授)方法を取って、やんわりかつ確実に予防策をはっていく方がいいと言えそうです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県によると、市町村が行ったがん検診の受診率は(平成20年度)、女性の乳がんは16.5%(全国14.7%)、子宮頸がんは29.2%(同19.4%)と3割以下。県がん対策推進計画では平成24年度までに受診率50%とうたっていますが、まだまだ目標達成には至っていません。乳がん検診では、年々受診率が下がってさえいます。検診を受けなかった理由として、「自覚症状がない」などの本人の意識の問題もありましたが、「検診場所・日時を知らない」「日時が合わない」「お金がかかる」といった受けやすい環境面が整っていないことが課題といえる理由も少なくありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳がん・子宮頸がん検診受診率(市町村実施分) ―千葉県健康福祉部健康づくり支援課より―
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| がん検診が受けられる場所・日時、知られていない 受けやすい環境づくりが大きな課題 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 長年、検診受診率アップに向けたキャンペーンを続けている乳がん体験者の会「アイビー千葉」の齋藤とし子代表は「いつどこに行ったら検診が受けられるかという情報をきちんと出すことが必要」と説明。平成21年度から始まった厚労省によるがん検診無料クーポンの配布で、受診率が上がった一番の理由は「どこで検診が受けられるか」という情報があらかじめ公開されていたことだといいます。従来の市町村実施のがん検診は、受ける側が申し込みハガキを送って初めて受診できる日時と場所、料金などの連絡が送られてくる段取り。しかもほとんどが平日の限られた時間帯に設定されており、集団検診では人数制限もあるため、検診を受けに行ったが受けられなかったというケースもあるほど。今野教授は「行政ももっと一生懸命やってほしい。我々は検診を受ける権利があるし、知らなかったから受けなかったということにならないようにしてほしい」と語りました。 乳がん検診は、全国的に40歳代からのマンモグラフィ検診が一般的ですが、千葉県では全国に先駆けて30歳代から超音波検査による検診を受けられる仕組みを取り入れました。千葉県がんセンターの山本尚人乳腺外科部長は「30歳から放射線を使ったマンモグラフィ検診を何度も受けるのは被爆の問題もある。何とか千葉県から乳がんの超音波検診の有用性を発信したいと考えている」と話し、できだけ若い世代から検診を受けられる受け皿を整えていく方向にあることを説明しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 未受診者は生命保険の保険料アップしたら・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方、検診を受ける側の意識も高くしていかなければとするのは、子宮頸がんの体験者でNPO法人・女性特有のガンのサポートグループ「オレンジティ」の河村裕美理事長。「検診を受けていない人はリスクが高くなるということで生命保険の保険料が高くなるとか、何かペナルティになるようなことがあれば行かなきゃという気持ちにもなる」と話し、検診に足を運ばざるをえないような仕掛けも必要との見方を示しました。 |
|
 |
|
| がん告知、だれから受けたい? 告知もチーム医療。ピア・カウンセラーの役割大 |
|
| パネルディスカッションでは「がんの告知を誰がするのがいいか」というテーマでも意見交換しました。 浜中理事長代行は自身が乳がんを告知された時の状況について「職場の病院の廊下でドクターからふいに『あれ、乳がんだったよ』と言われ、心構えも何もなく頭の中が真っ白になった」と思い返しながら、「患者は、ドクターに一方的にいきなりがんを宣告されてもその先はもう聞いていない。それより同じがんを体験した看護師などから言われた方がクッションがあっていい」と話し、告知はむしろ患者さんにより近い存在である体験者からされる方が衝撃も少ないのではないかと提案しました。 一方、やはり医師が告知すべきとの意見もありました。オレンジティの河村理事長も初めて自分が子宮頸がんだと聞いたのは内診を受けている最中に医師がつぶやいた一言だったことを振り返り、「最初は絶対に嘘だと思ったが、やはり告知は医師が責任を持って行ってほしい。その時に治療のこと、不安なことなどを聞ける患者会の紹介なども合わせてするといいのではないか」と話し、患者さんへのフォローを考えながら医師が告知する方法を求めました。千葉県がんセンターの田中婦人科部長は、医師は告知の後に治療に向けた要点も説明しなければいけないしじっくり時間をかけて患者さんの気持ちに向き合う余裕がない場合もあるとの現実を説明し、「告知もチーム医療。患者さんの気持ちをゆっくり聞ける看護師やピアカウンセラーの方にゆだねることもあっていいのではないか」としました。 千葉県がんセンターでピアカウンセラーを務めるアイビー千葉の齋藤代表は「体験者として患者さんの気持ちを丁寧に聞くことができる。一回ではなく何回も話をし時間をかけて落ち着く場合もある」と話し、告知の後のフォローが重要であるとしました。同センター乳がん看護認定看護師の西弘美さんは「患者さんの気分を見ながらゆっくり話をするようにしている」とし、同センター地域医療連携室の丹内智美副看護師長も「地域の病院や診療所などでがんの診断を受けてからがんセンターに検査に訪れる患者さんもいる。がんセンターで検査を受ける前であっても不安をやわらげることができるように、がんセンターの相談支援センターを利用できることをPRしている」と話し、告知を受けた患者さんの心のケアを優先した対応をする受け皿があることを説明しました。 |
|
 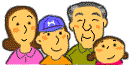  |
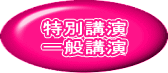 |
| 第3回市民公開講座「ストップ!女性のがん 早期発見がすべてです」では、パネルディスカッションのほかに特別講演と一般講演が行われ、7人の講師が医師、看護師、患者さんの立場で乳がん、子宮頸がん、地域医療連携をテーマに講演を行いました。プログラムと講演要旨、配布資料などを掲載しますので、ご覧ください。 |
    |
| 当日は、多数のご参加ありがとうございました。 今後ともNPO法人・医療福祉ネットワーク千葉をどうかよろしくお願いいたします。 講演の感想、がん全般、乳がん、子宮頸がんについてのご意見などありましたらぜひメールにてご連絡ください |
 katagiri@medicalwel.com katagiri@medicalwel.com |