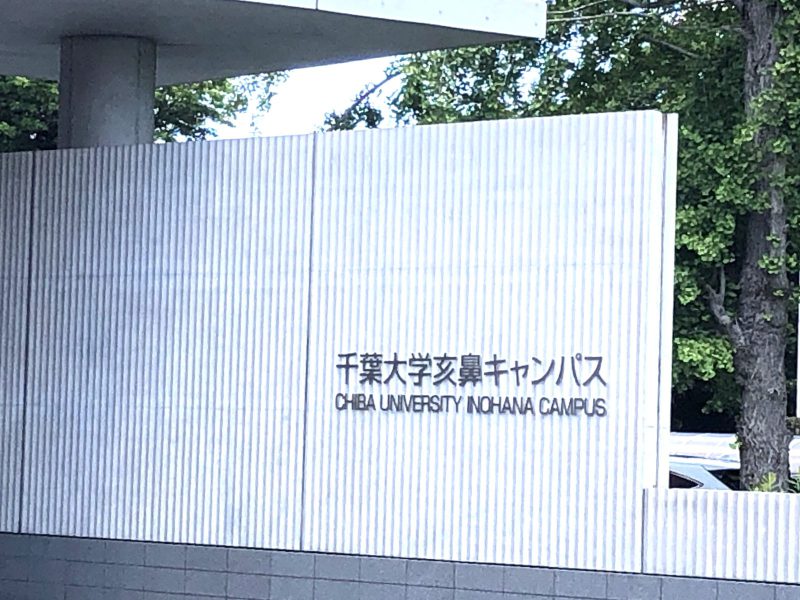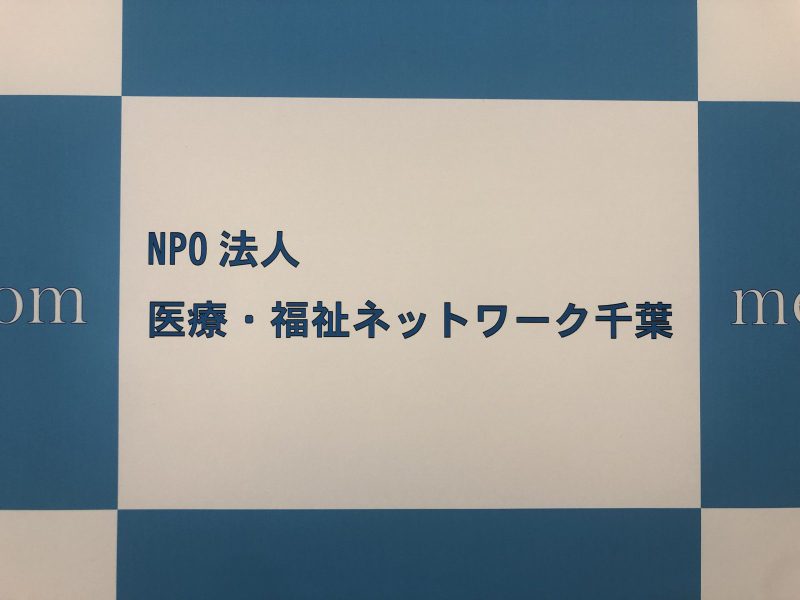【Dr.竜のよもやま話】今年で創立150年を迎える千葉大学医学部。関東圏の医療を支え続ける存在として
千葉大学医学部は明治7(1874)年に創立され、本年で150年を迎える。明治政府は、明治7年に「各大学区に医学校1か所を置き病院を属す」と交付した。これを受け、同年千葉に病院が設置された。その後、明治15(1882)年に県立千葉医学校になり、大正期に千葉医大となった。戦後の学制改革により、新生千葉大学が設立され、千葉大学医学部になったのである。
1920年の大学令で国立大学に昇格
明治7年の明治政府の交付により、全国的に医学校は多く創立され、5年後の明治12年には全国で48校もあった(官立2、公立21、私立25)。私立は明治8年に始まった医術開業試験の予備校としての私塾が基礎となっており、のちに日本医大となる済生学舎、東京慈恵医大になる成医会講習所などがある。しかし、多くの医学校は、明治政府の予算不足などにより廃校になった。埼玉医学校は明治12年に廃校、茨城医学校は明治19年に廃校などである。いくつかの存続した医学校のうち、1920年の大学令により、国立大学に昇格した医学校は千葉、新潟、金沢、岡山、長崎、熊本で、いわゆる「旧六」と呼ばれている。
明治元年に東京に帝国大学が1校誕生しているが、明治19(1886)年の帝国大学令で東京以外に、北海道、東北、名古屋、大阪、京都、九州などに帝国大学が設置され、各大学に医学部が設置された。私学では、日本医科大学が明治9(1876)年、東京慈恵医科大学が明治15(1882)年、慶応義塾大学医学部が大正6(1917)年に開院している。このようにみてみると、千葉大学医学部(千葉医大)は日本医学の最前線にあって、戦前戦後と、東大、慈恵医大、慶応医学部、日本医大など関東全体の医療を支えていた存在だったのである。